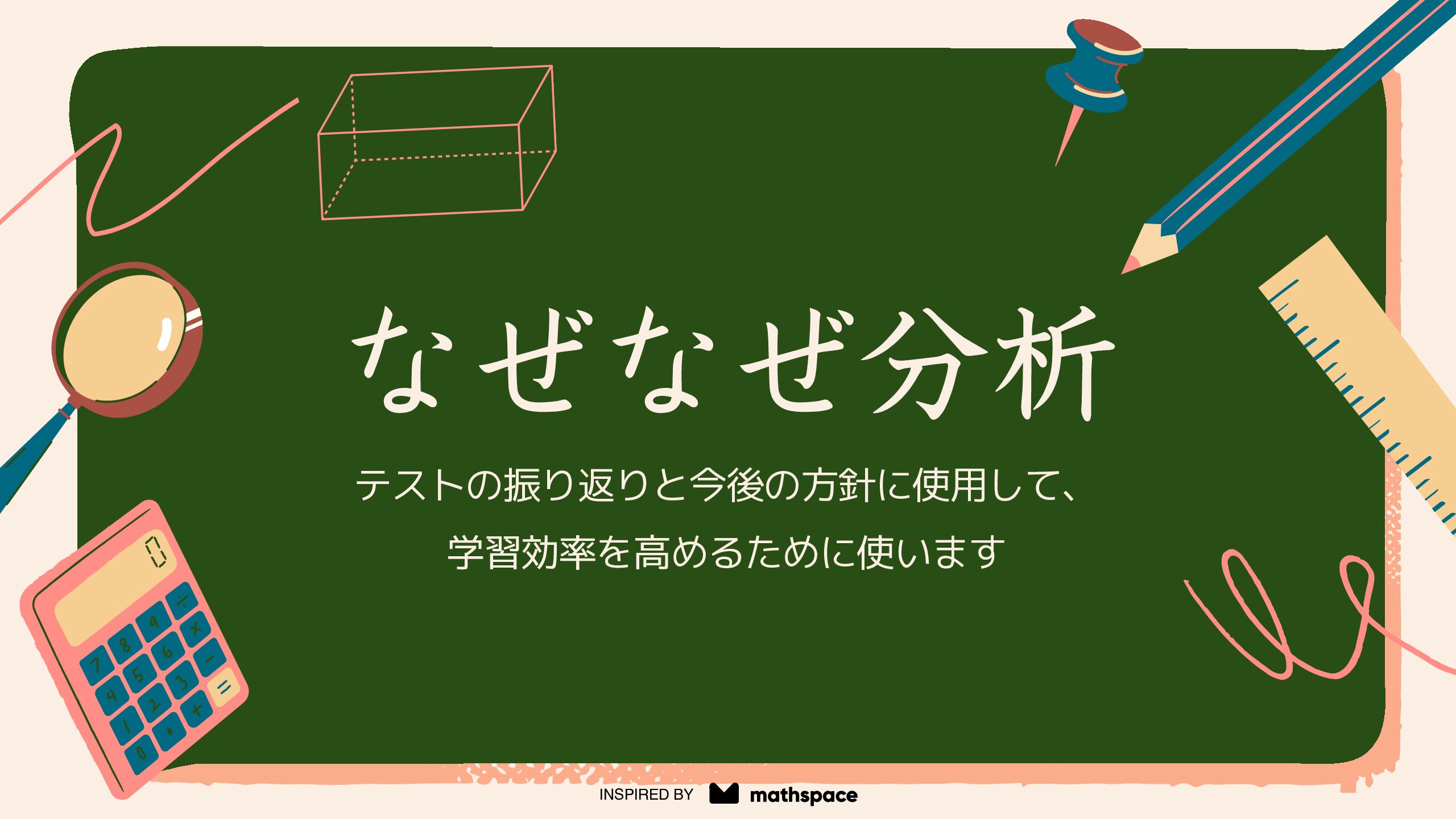みなさん、こんにちは。
本日は表題の件に関して考えていきたいと思います。
結論を先にお伝えすると、『老子』の第11章と『WHITE SPACE ホワイトスペース仕事も人生もうまくいく空白時間術』では空白が有を生むという点で共通しておりました。
では、その考え方を見ていきましょう。
『老子』第11章
部屋というものは、戸や窓をくり抜いてこしらえるが、]そのまん中に無の空間が空いている。だからこそ、[部屋は人々が出入りして]その役割を果たすことができるのだ。
池田知久.老子全訳注.2019.p46
『老子』は第7章で述べているように、先頭に立たないことが、かえって先頭に立つことができるなど、”無”が”有”を生むと言った逆説的な考え方をしています。
今回取り上げる11章でも、”有”と”無”の対比が扱われていて
部屋には、壁、床、窓や扉のほかに、”無”の空間が有るから善いのだ。と述べています。
雪国出身らしく考えてみると、雪が積んであれば雪山、そこに穴をほって住めるように雪ではない空間を作るから、かまくらとして住居(?)や観光資源としても使えるということかなと考えています。
ここでは、老子が無を作るからこそ有が生まれると述べていることを気に留めていただければと思います。
ホワイトスペースの序文
夫が戻るまでの20分間、私たちは手に入るかぎりの燃料を隙間なくきっちり積み上げ、マッチを投げ込んで火を熾せずにいた。
ジェエット・ファント.WHITE SPACEホワイトスペース仕事も人生もうまくいく空白時間術.p22
この一文は、作者がアウトドアに訪れたときの体験で、注目すべきは”隙間なくきっちり積み上げた”こととなります。これを老子の”有”と”無”で当てはめて考えると、材料だけで満たされた”有”だけの空間と考えることができます。
本書では、この後夫が松葉をふんわり盛り付ける、着火剤を互い違いに重ね合わせるなど、空気の通り道を作ることで、焚き火の着火に成功したとのことです。そこで作者は空気の通り道がないから、酸素を供給することができなかったことに気づきます。
“無”の空間があるからこそ、役割を果たす酸素が”有る”状態になったと解釈して間違えないかと思います。
末尾
今回は”無”が有用性を生み出すという共通点を紹介させていただきました。
ジェリエント・ファントさんの気づきのきっかけが空気の通り”道”であり、同じく『老子』も道を体現するためには…するのが善いと道について論じている様子が個人的に面白いかなと考えています。
私も身近なことで考えるとするなら、
山積みになった本達や本で敷き詰められた本棚でしょうか。
片付けたときにしか、”無”が生み出す”有”の効果はわからないかもしれません笑


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2146c5f4.08e34074.2146c5f5.159ee471/?me_id=1213310&item_id=20722728&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4076%2F9784492224076_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)